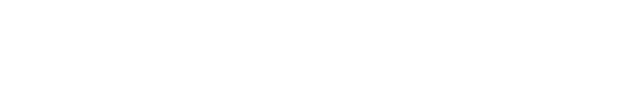歯並びってどうやって決まる? ~デコボコや出っ歯などの不正咬合が生じるメカニズム~
コラムでは歯並びに対する悩みや治療するうえで理解していただきたい事を中心に掲載していきたいと思います。
第1回は、なぜ歯並びが悪くなってしまうのかという事についてお話したいと思います。
歯並びを決める重要な因子として
1.上顎、下顎の骨格的バランス
2.顎と歯の大きさの調和がとれているか(歯と顎の大きさのバランス)
3.歯の周りの筋肉のバランス(舌など、歯並びの内側の筋肉と頬や口唇など、歯並びの外側の筋肉のバランス)
があります。
1番と2番に関しては一度不正が出てしまっていると、矯正歯科医が介在して治療しないと治らないところであるので、
患者さんや治療を受ける前の方に知ってほしいところとしては3番の歯の周りの筋肉のバランスという点になります。
1番の骨格的因子に関しては、上顎と下顎のバランスが悪いと歯並びも同じようにズレうまく噛めないことが多いです。
成長期であればある程度コントロールして調和を取ることが出来ますが、成人の方では骨格のコントロールは一般的な歯科矯正治療では難しいです。(上顎と下顎のずれが大きい人に対しては顎変形症という手術の対象となりますが)
成人の方だと、ずれた骨格に歯並びを合わせるように咬合を作っていきます。
2番に関しては、歯の大きさの方が顎より大きい場合歯が上手く並びきらず、歯並びがガタガタになり歯磨きが上手くできなかったり、ある一点でしか噛めず、負担がかかってしまうようなかみ合わせになっていることが多いです。
歯が綺麗に並ぶためのスペースを歯並びを広げたり、時には歯を抜いたりすることによって、かみ合わせを作っていきます。
そこで本題の3番ですが、
3番の周囲の筋肉によって歯並びが決まるという点は皆さんご存じだったでしょうか?
もう50年ほど前からBrodieという方により唱えられているバクシネータメカニズムという考え方です。
現在でもこの周囲の筋肉のことを考慮せず矯正治療すると治療が上手くいかず、装置を外した後に元に戻る可能性が高くなってしまいます。
このバクシネータメカニズムとはどういうものかというと
歯並びの外側はピンクで示されているように
筋肉で内側からも外側からも囲まれており
その内側の筋肉と外側の筋肉のバランスが取れたところに歯は並んでいるという考え方です。
このメカニズムが失われた代表的な例が指しゃぶりです。
指しゃぶりを長期間続けていると、
内側の筋肉である舌が機能を果たさず本来、U字形の形であるはずの歯並びが、V字形の歯並び
になります。
本来の理想的な歯並びの形(U字型)と内側の筋肉より外側の筋肉が勝り細長くなった歯並び(V字型)
細長くなると、前歯が前方に出ていわゆる出っ歯さんのような歯並びになります。
その他にも、よくお口がぽかんと空いている子は外側の筋肉である唇の筋肉が作用しなくなり、度合いによっては歯並びが崩れる可能性があります。
成人の方でも、下唇に型がつくほど下唇を咬み、歯並びが崩れる、口呼吸の方は歯並びが崩れやすいなど筋肉と歯並びの関係が密接な関係があることは間違いないと考えています。
治療を受けられる前の方は、なるべく歯並びが悪くなる癖をしないように意識し、歯並びが悪化しないようにすること
すでに治療を受けている方や治療が終わった方は、歯並びが悪くなる癖が残っていると元に戻りやすくなるので、歯並びが悪くなる癖をしないように矯正歯科医師としないためのコツや方法をご相談いただければと思います。
長くなりましたが、意外と歯並びに影響のある歯並び周囲の筋肉のお話でした。